みなさん、こんにちは。社畜のとんかばです。
本日は新NISA投資上限枠は最短で使い切るべきかという疑問に対する僕の意見と理由を紹介させて頂きます。
記事紹介
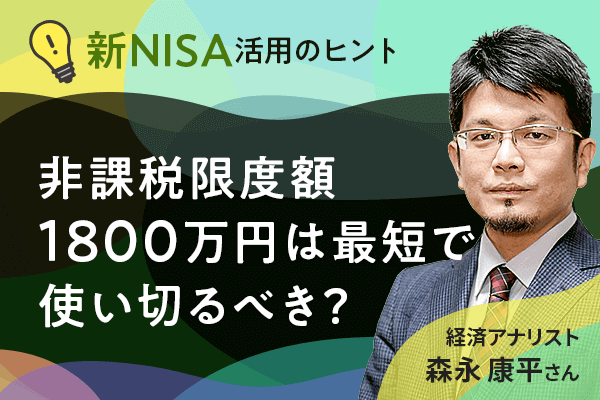
上記の記事では経済アナリストの森永康平氏がNISAをもっとうまく使いこなすポイントとして、新NISAで拡充されたポイント、つみたて投資枠・成長投資枠の使い分けの必要性、新NISA投資上限枠は最短で使い切るべきかについての考えを紹介されています。
森永康平氏はYouTubeをはじめとした様々な動画や記事で経済・金融・投資について説明されており、非常にわかりやすく的確で正しい内容や説明ばかりです。個人的には普段から大変勉強させて頂いており、非常に感謝しています。
無理に最短で使い切る必要はない
記事の最後では「新NISAの非課税限度保有限度額である1,800万円を最短で使い切った方がいい」という意見に対して、森永氏は以下のように述べています。
つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は240万円がそれぞれ年間の投資可能上限額となっていますから、合計で年間360万円の投資が可能です。よって、1,800万円の枠を最短で使い切るには、5年間かかるといえます。
ではなぜ、最短で投資枠を使い切るべき、という主張なのかというと、そうすることで元本に対する複利の効果を最大限享受できるから、というのです。
たしかに、複利の効果は投資期間が長くなれば長くなるほど、雪だるま式に効いてきます。しかし、それは投資を開始してからプラスのリターンがずっと続けば、というのが大前提であって、当然ながらそんなに都合よく株式市場は動きません。
よく投資には分散が重要だといわれますが、これは投資対象を分散することでリスクを低減させましょう、というだけではありません。時間を分散することでもリスクを低減させましょう、という意味も含んでいます。
5年間で投資枠を使い切るということは、30年、40年という投資期間において、最初の5年間だけの株価水準に賭けることを意味します。私は、投資枠はしっかりと長期にわたって延々とつみたて投資をするべきだと考えます。
非常に分かりやすい説明ですね。インデックス投資は「投資のタイミングは誰にも読めない」「インデックス投資は長期的に右肩上がり」が前提です。論理的には「余剰資金はできるだけ速やかに多く入金する」「できるだけ速やかに多く投資枠を利用する」ことが最適解となります。
一方で、これは「投資枠を最短で利用するための余剰資金が用意できる」「投資枠をリスク資産で全て利用するほどのリスクをとれる」などの場合に限られます。ある程度の無リスク資産を用意しておかなくてはならない人や余剰資金を用意できるほどの入金力が無い人は無理する必要はありません。むしろ現在の生活を圧迫したり、自身のリスク許容度を超えてしまう可能性が高いです。
また、投資初心者の人やリスク許容度の低い人の場合、短い期間で大きな金額を投資することに対してまだ慣れておらず、精神的な負担から狼狽売りや不合理な行動をとってしまったり、日常生活に悪影響を及ぼす可能性があります。その場合、少ない金額の積立から始めて長期で継続したり、焦らず徐々に積立金額を増やす方が良いと思います。
例えば「自分は毎月の金額をいくらぐらい投資に回して大丈夫か、その金額をどのくらいの期間かけて続けることができるのか、最終的にはいつまでにどのくらいの資産金額まで辿り着きたいのか」についてイメージしてみると良いでしょう。
結論、僕の意見は「無理に最短で使い切る必要はない」「リスク許容度の範囲内で資金の余裕があれば最短でできるだけ早く多く投資枠を利用した方が良い」「人によっては少ない積立金額から始めて長期で続けたり徐々に金額を増やす方が良い」となります。みなさんの資産形成の参考にして頂けると幸いです。
まとめ
本日は新NISA投資上限枠は最短で使い切るべきかという疑問に対する僕の意見と理由を紹介させて頂きました。
新NISAの投資枠は無理に最短で使い切る必要はありません。
自分のリスク許容度や余剰資金に応じて適切に利用しましょう。



コメント